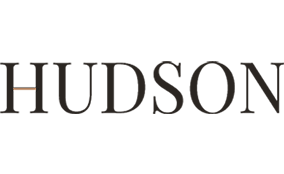5年後10年後も続く愛される定番として④
3色目の展開カラーはチャコールグレーの器を黒の代わりに。 The third color chose a charcoal gray instead of black. [caption id="attachment_11999" align="alignnone" width="300"] グレーの器を展開し始めた時、最初に選んだ4型 charcoal gray was initially chosen in these 4 models[/caption] 黒が思い通りの色にならなくて探していたことはプロダクトフィロソフィーのブログ<5年後10年後も続く愛される定番として①>でも記載しましたが、その後いったん黒を作ることを保留にした時に、代わりに気になって選んだのがこちらの写真のグレーの土です。 In my blog post titled "As a Timeless Classic That Will Continue to be Loved 5 Years and 10 Years from Now - Part 1," I mentioned that I was searching for the perfect shade of black but was unable to find it. However, during the period when I temporarily put the black color on hold, I became intrigued by the gray clay featured in the attached photo. それでも、黒じゃないにしても黒っぽい器が作りたい気持ちは変わらずにありました。 Nevertheless, my desire to create a container that had a blackish appearance persisted, even if it wasn't actually black. 豆腐料理、冷やしうどん、大根おろしポタージュスープなどの白っぽい料理にはやはり白い器より黒っぽい器の方がおいしそうに見えるからです。 グレーで作ってみると、土に入っている御影石の独特の表面感も相まって和洋折衷な料理に合わせやすい器となりました。 such as tofu dishes, chilled udon, and dishes with grated daikon or potage soup, tend to look more appetizing in vessels that have a blackish hue rather than pure white. When I experimented with creating gray vessels, the unique surface texture of the small stones complemented a variety of dishes that fuse Japanese and Western flavors. This versatility makes...
Read More